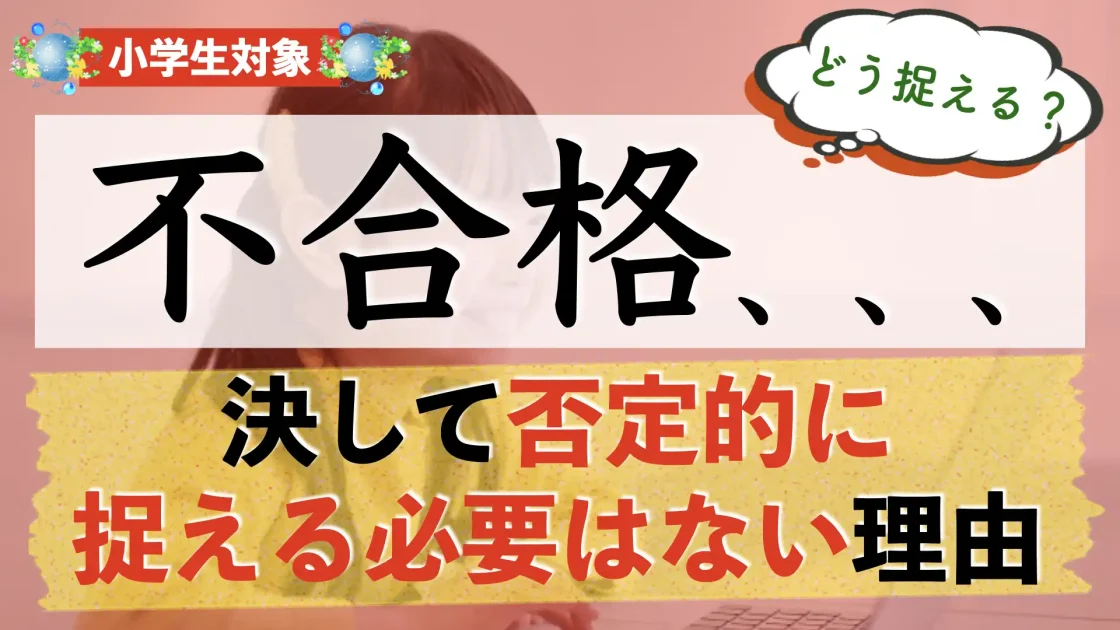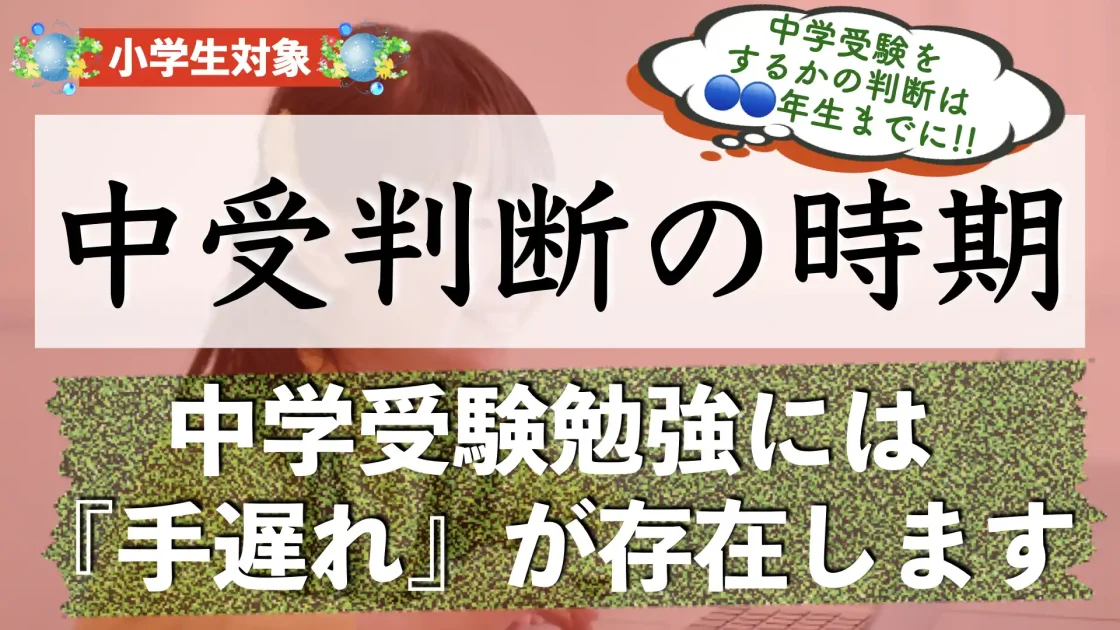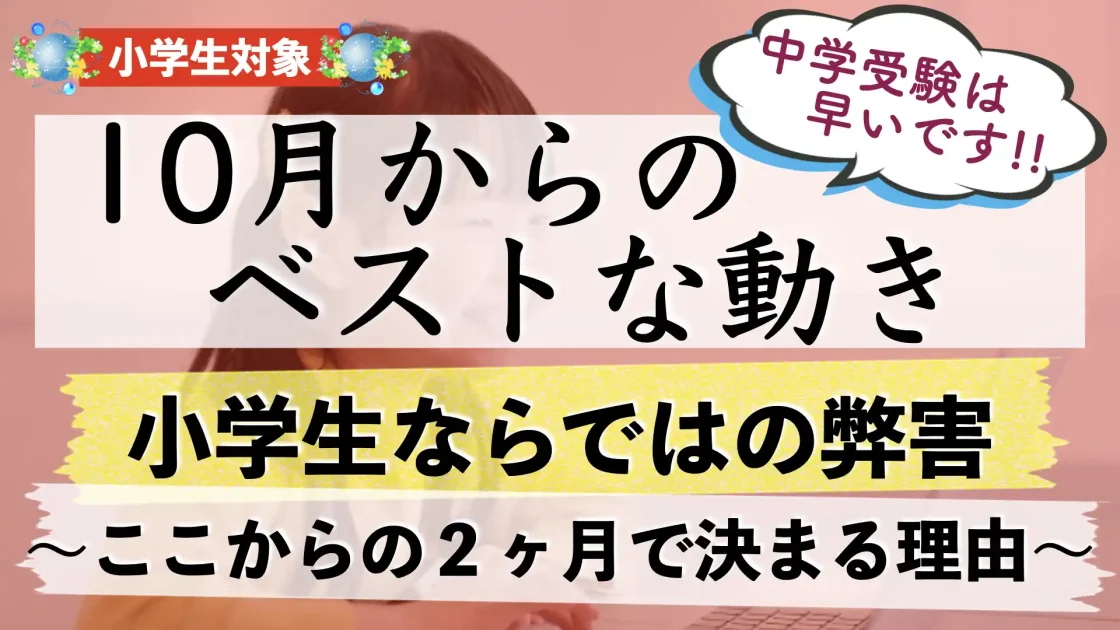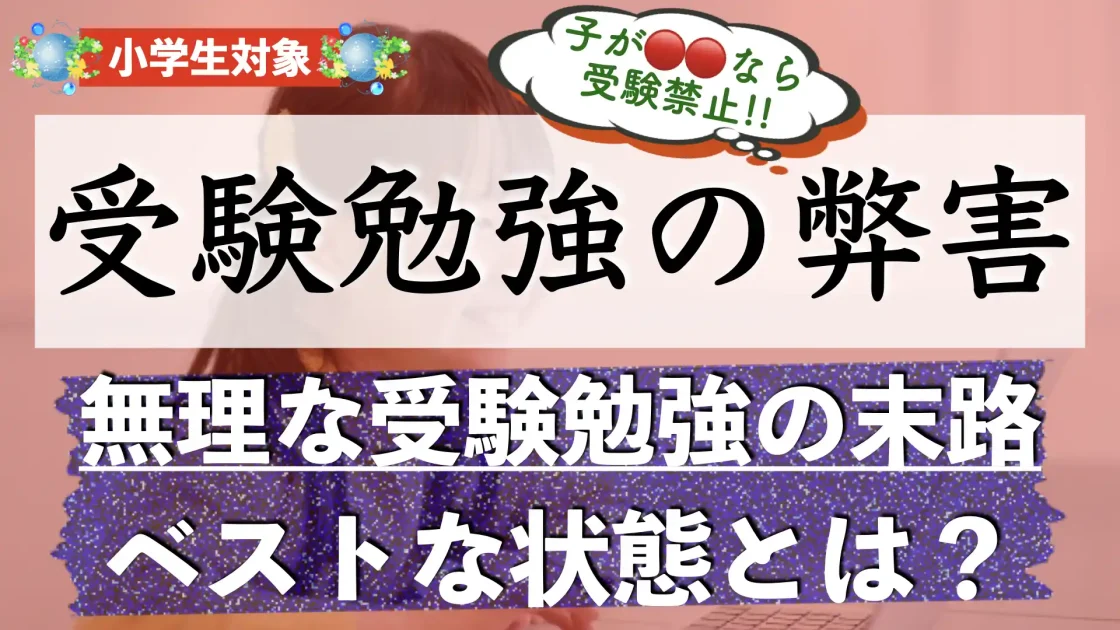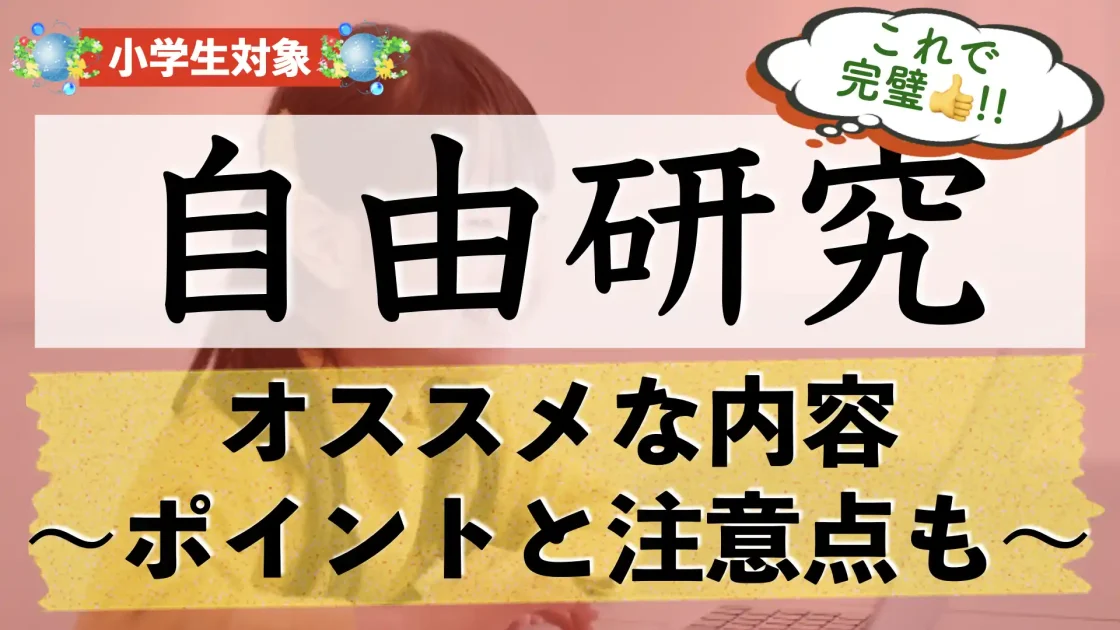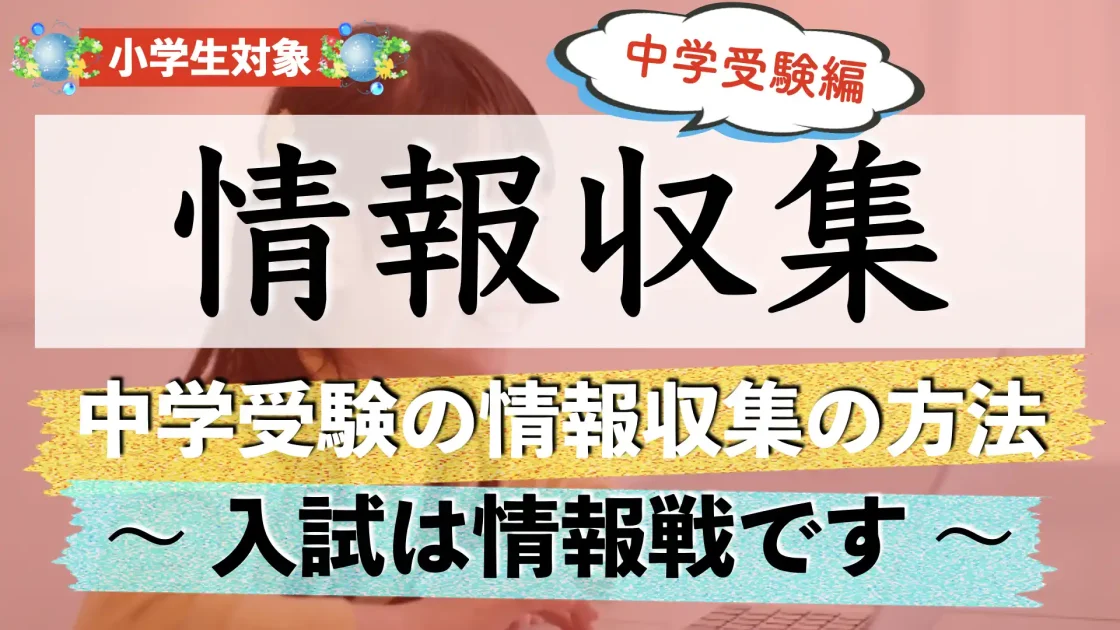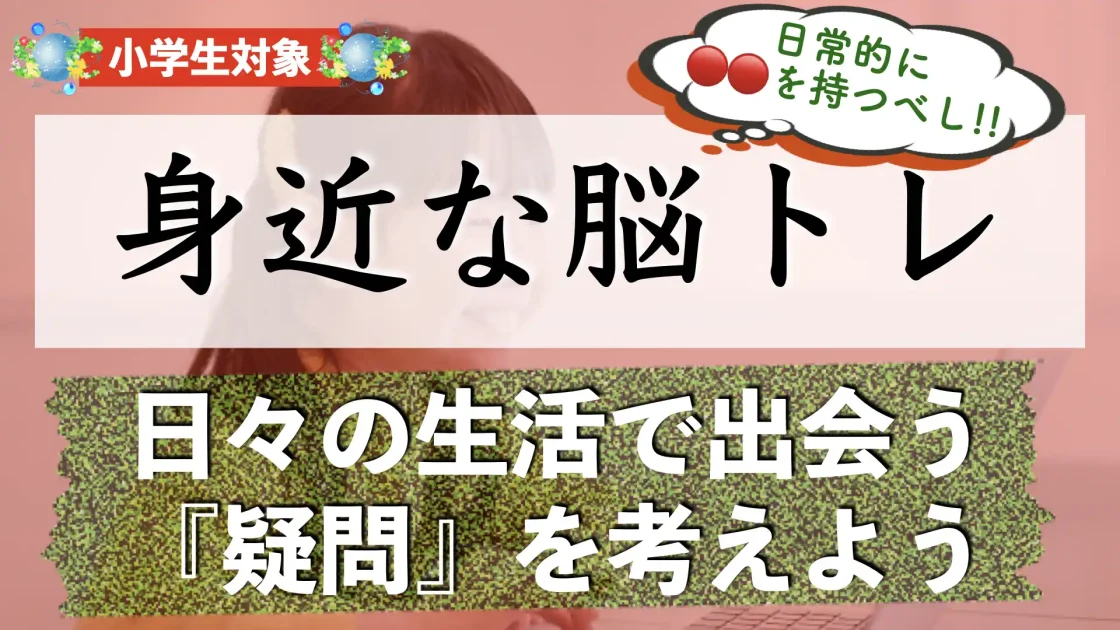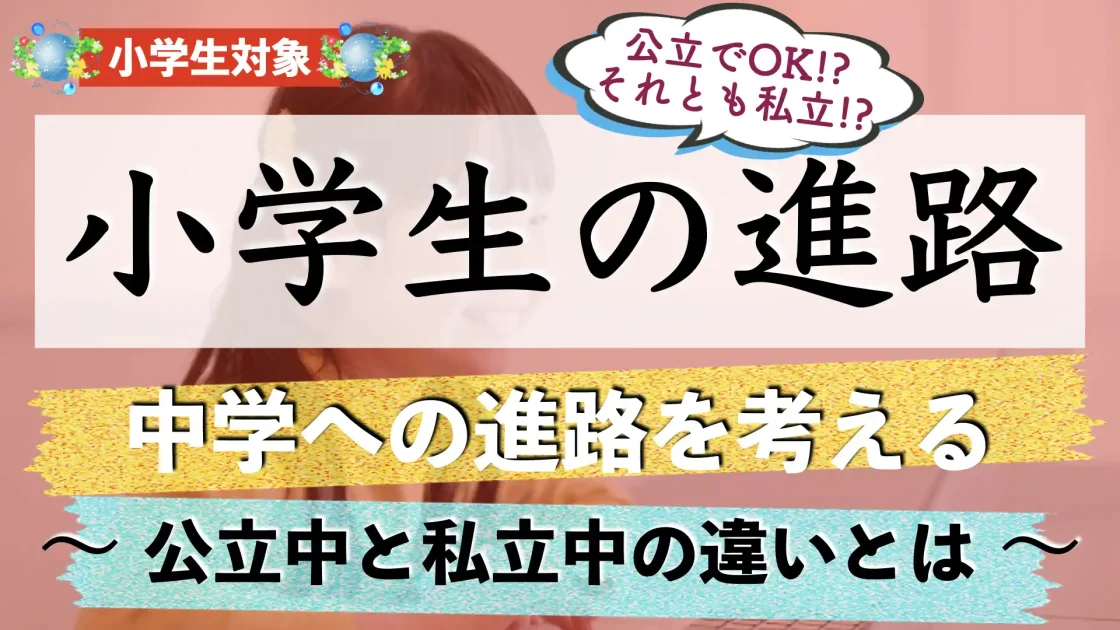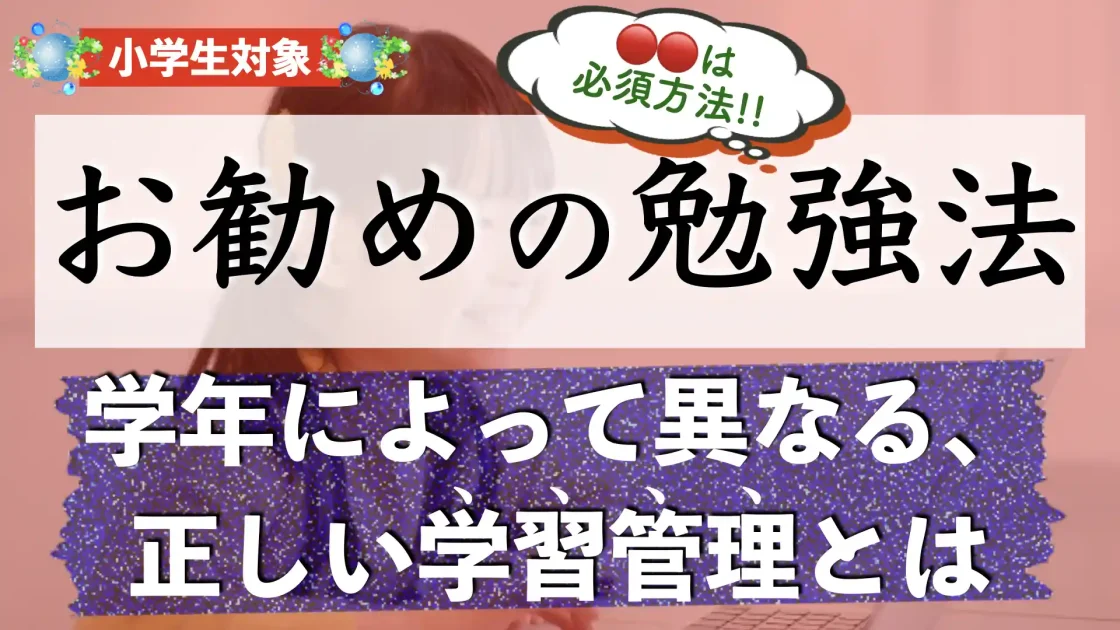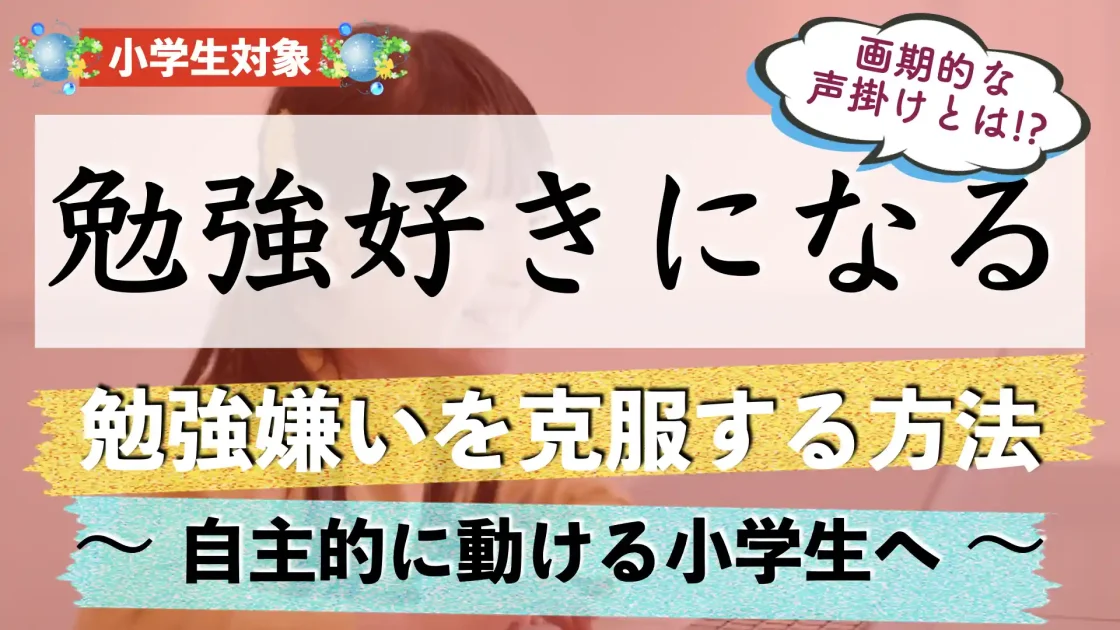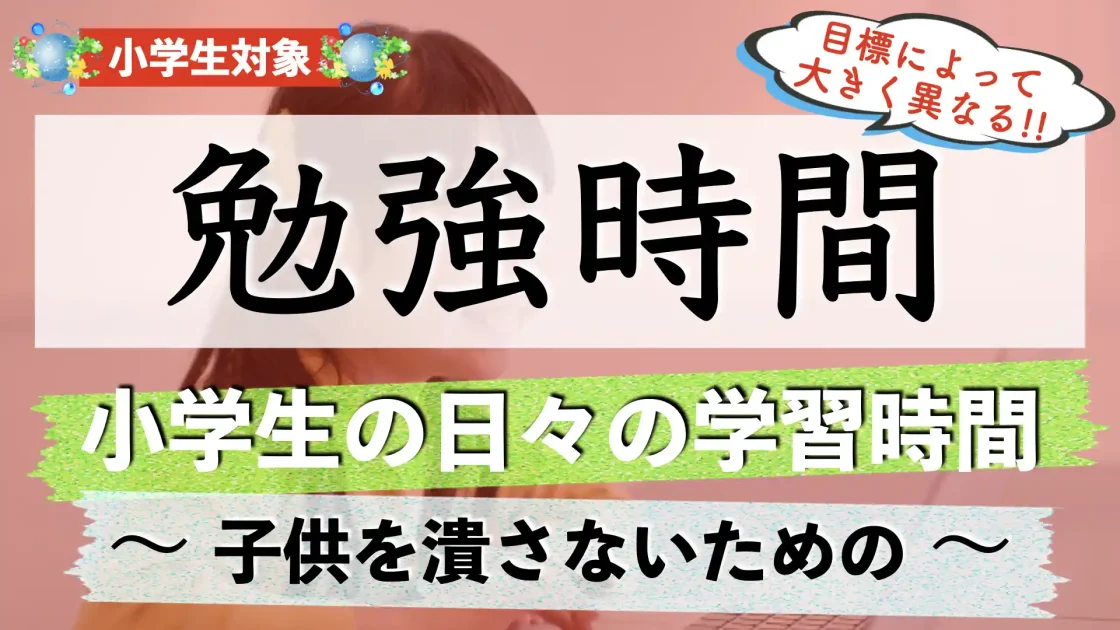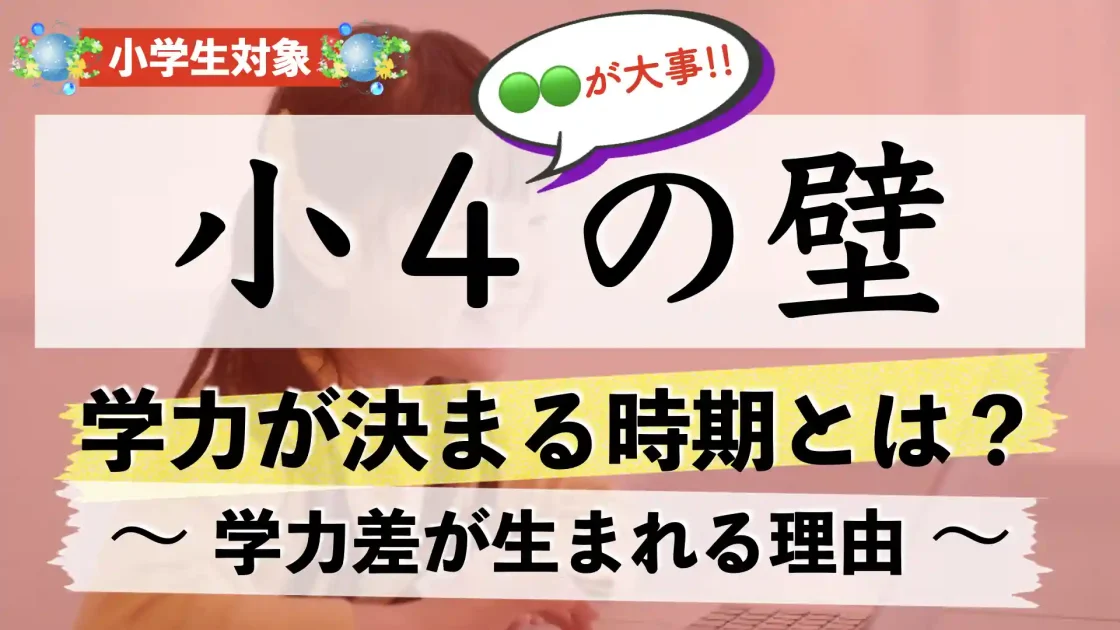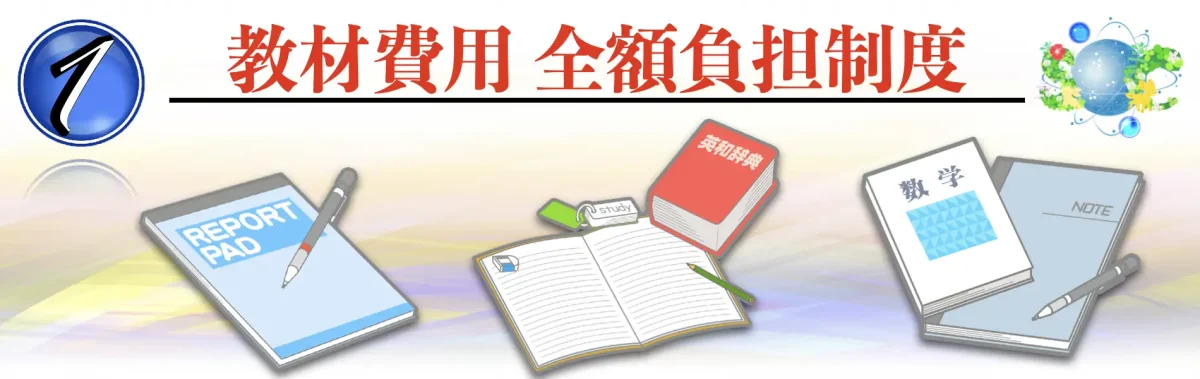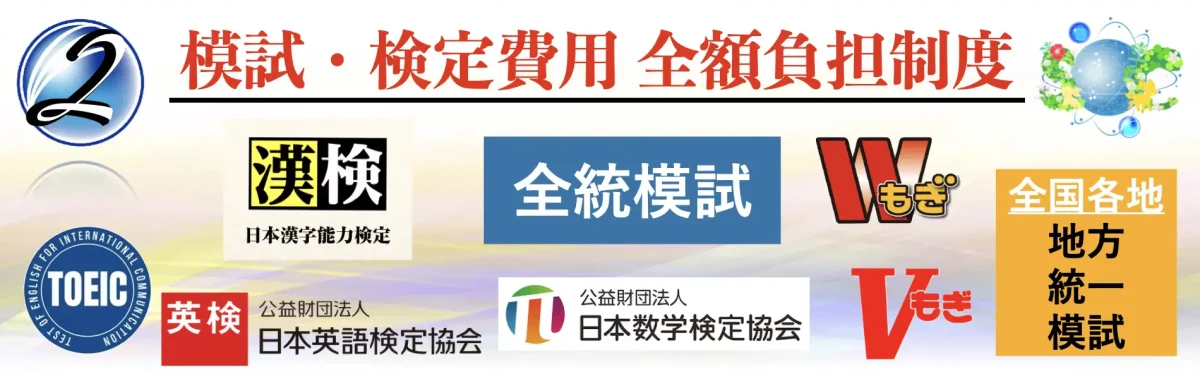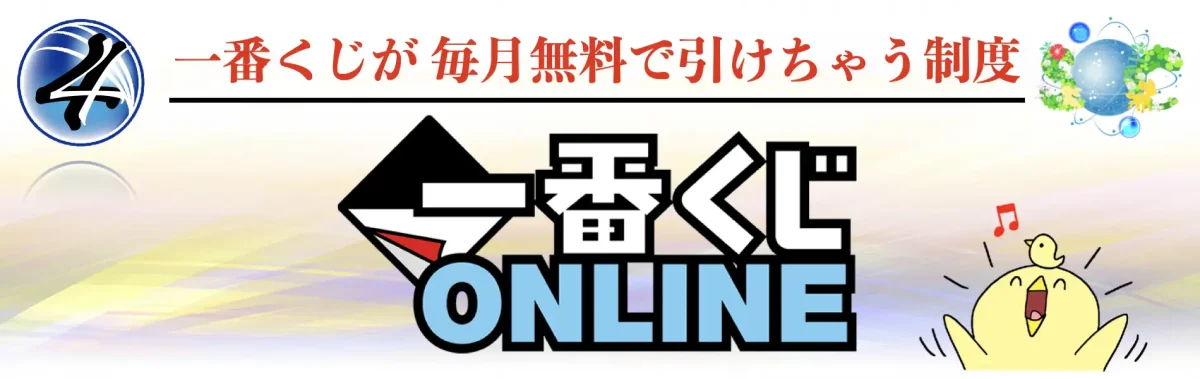【中学受験】小6の秋から学力は伸びる?|10月・11月のベストな勉強方法とは?
目次
【中学受験】小6の秋から学力は伸びる?

勉強方法次第ではまだまだ学力は伸びる
中学受験において、小6の秋から学力を伸ばすためには「勉強方法」について考える必要があります。
時期に関わらず、そもそも中学受験をするにあたって解いておくべき問題は、大きく分けて「基礎問題」と「応用問題」に分かれます。
小6の秋以前からスケジュールを立てて中学受験に向けて勉強をしているならば、小6の秋には「基礎問題」がほぼ完璧に解けるようになっているはずです。
「基礎問題」を多く解いてきたことにより十分な知識を持っていることを前提として考えるならば、秋からは「応用問題」をなるべく多く解くことでまだまだ学力は伸びていくでしょう。
また、多くの場合で中学受験は12月下旬から2月上旬に実施されます。
受験当日から逆算して考えても、少なくとも小6の秋から約3ヶ月の間には「応用問題」に手を付け、学力を飛躍させる必要があるでしょう。
●基礎問題を反復すべきなのはこんな人!
志望校の偏差値が55以下の人の場合、そもそも応用問題の出題率が低いため、その練習をしてもあまり効果がありません。
また、現時点で基礎に不安がある人は、受験本番において応用問題で得点することは簡単ではないため、応用問題の訓練の優先順位は低いと言えます。
まだ学力が足りていないと感じる人は、まずは基礎知識をしっかり頭に叩き込むことを意識し、基礎問題で確実に点数が取れるように動いていきましょう。
中学受験の10月・11月のベストな勉強方法とは?

基礎知識の反復をルーティーン化する
中学受験に対する10月以降の勉強方法において、いわゆる「基礎問題」は知識の反復確認程度に留めるかわりに習慣化させることが大切です。
知識の反復確認をルーティーン化することで、応用問題をマイペースにじっくりと解く時間を作ることができます。
また、応用問題ばかりを練習して知識の反復確認を怠ってしまった場合、せっかく定着していた基礎問題で得点できなくなります。
人間誰でも反復確認をしなければ、次第に物事を忘れてしまうものです。
基礎知識が疎かにならないよう知識の反復確認を行いつつ、応用問題に手を付ける時間を創出しましょう。
志望校の過去問に取り掛かる
中学受験の約3ヶ月前となる10月以降に、いよいよ志望校の過去問に取り掛かり始めましょう。
いくら基礎問題ができていたところで、志望校の過去問を解かなければ傾向を掴めずに、解くべき問題の優先順位を見誤ってしまいます。
受験する学校によっては癖のある問題を出題するところもあるので、志望校の過去問を解くことは必要不可欠です。
「どんな問題が出題される傾向にあるのか」「自分の持っている知識をどのように問われるのか」「そもそも知識を持っているのかいないのか」を意識し確認しながら、基礎が定着している10月以降のタイミングで志望校の過去問を解いていくことをおすすめします。
模試を総復習(反復)する
中学受験に向けた10月以降の勉強方法として、これまで受けた模試を総復習するのも一つの手です。
模試の総復習は、「基礎問題と応用問題の両方の出題方法と解法を丸ごと覚えることができる」「該当する科目の問題に対する一連の流れに慣れることができる」など、メリットしかありません。
実戦形式の問題と対峙することができ、なおかつ問題を反復することが可能なので、知識が増えている秋以降の勉強方法としてぴったりです。
また、模試の間違えた問題の解説を読んでも理解が進まない場合には、基礎力が不足している可能性が高いので、知識を叩き込み直す動きを練ることもできます。
基礎力が足りているかどうかの確認や応用問題への慣れに繋がるので、ぜひ模試を総復習し反復しましょう。
苦手な単元は線引き(悪く言うと捨てる)し得意な単元を伸ばす
中学受験への10月以降の勉強方法として、苦手な単元はある程度線引きした上で得意な単元を伸ばす努力をしましょう。
勉強以外にも言えますが、苦手なものを克服するにはそれ相応の時間や惜しみない努力が必要です。
中学受験の約3ヶ月前となる秋頃の限られた時間の中で、ひたすら苦手な単元の問題ばかりを解いていくのは少々効率が悪くナンセンスです。
したがって、苦手な単元に対する勉強はある程度のところで留め、完璧にするという意識よりも、もはや残りは捨てた方が効率良く学力全体を伸ばすことができるでしょう。
中学受験の約3ヶ月前なら苦手な単元はある程度目処がついているはずなので、これまでと少し思考を変えて線引きをする単元を選定することも視野に入れましょう。
また、線引きした方が良いのはあくまでも苦手な「単元」であって、苦手な「科目」ではありません。
意識として苦手な科目は存在するかもしれませんが、基本的に科目丸ごと捨てるようなことはあってはいけないので勘違いしないようにしましょう。
中学受験に向けた10月・11月によくあること

勉強量が増え悩んでしまう
中学受験に向けた10月以降では、自分が10月にあるべき姿と現実との学力のギャップから、やらなければならない勉強量が増えてしまうということが起こりがちです。
場合にもよりますが、その場合は逆に勉強量を減らすなどの調整をする方が良い場合もあります。
「全ての勉強をガッツリやる」という意識から、「基礎知識の部分は軽く反復する程度に留める」ように意識することで、本来勉強に費やそうと思っていたエネルギーが小さくなり、精神的にも少し解放されるようになります。
したがって、勉強のやり方一つを変えれば費やすべきエネルギーが変化するので、「勉強量が増えていく...どうしよう...」という悩みから解き放たれ、かえって勉強に集中することができる場合があります。
思うように結果が出ない
本来なら夏までの勉強の努力が秋頃には実ってくるはずですが、思うように結果が出ない場合もあります。
結果が出ない場合は、なぜ思い通りの結果が出ないのかを冷静に分析することが必要です。
結果が出ない(問題に正解できない)原因には、例えば「基礎知識が不足している」「配点の大きい応用問題で得点できていない」「時間が足りずに問題が解けない」「模試当日の体調が悪い」など多岐に渡ります。
結果に対して一喜一憂する前に、様々な側面からなぜ結果が出ないのかを冷静になって分析し、結果を出すためにどうしたらいいのかの対策を立てましょう。
プレッシャーを抱える
小6の生徒にとって、受験というのは人生で初めての人がほとんどでしょう。
さらに言えば、これまでの「人生」の中で初めての大きな障壁とも言えるでしょう。
したがって、中学受験をする生徒には保護者の方々が想像する以上のプレッシャーがかかっているケースも少なくありません。
受験はある種「自分との戦い」にもなるので、メンタルマネジメントが必要です。
小6の生徒に自分自身のメンタルマネジメントを要求するのは非常に難しいので、周囲が手助けをし、生徒の立場に立って傾聴し課題を解決してあげる必要があるでしょう。
体調管理が疎かになる
中学受験が差し迫った10月以降において、意外と疎かになりがちなのが体調管理です。
当たり前ですが、健康な体がなければ勉強もできず、そもそも受験をすることができなくなってしまいます。
体調を崩してしまう主な要因は個人によりますが、一般的には流行り病(新型コロナやインフルエンザなど)、寝不足や不摂生な生活、怪我などが挙げられます。
特に、感染症は受験シーズンの冬にかけて流行しがちなので、マスクの装着や手洗いうがいを徹底するなどの対策が必要です。
また、ゲームやスマホ動画は寝不足や不摂生な生活に加えて、時間の浪費に繋がってしまいます。
体調を崩してしまった結果、普段の学習ペースが乱されモチベーションが著しく低下するという人も少なくありません。
学力とは別に、「体調を崩したせいで結果が出なかった」というようなことにならないように注意しましょう。
小学生対象記事一覧
オンライン授業で効率良く成績UPしてみませんか?

通塾コスト0!オンラインで1対1のリアルタイムの授業が受けられる!
スタディングクラウドは、全国(全世界)を対象にオンラインで授業を行う個別指導塾です。
家庭教師とオンライン塾でお悩みの場合、お住まいの地域性により授業の質が担保できない、家での対面式であることが不安など、様々な懸念点があるかと思います。
スタディングクラウドは、オンライン授業ならではの柔軟な指導方法・教材・カリキュラムを構築することができ、完全個別指導(1対1)なので従来の学習塾よりもご家庭や生徒様の希望にフォーカスすることができます。
さらに、全国(全世界)を対象に授業を行っているので、お住まいの地域性による制約等はなく(日本国外に在住の方ももちろん可能です)、多くの方にご好評をいただいています!
もし、少しでもスタディングクラウドが気になるという方は、ぜひ一度お問合せフォームから資料請求、もしくはお問合せしてみてはいかがでしょうか。
お問い合わせ
スタディングクラウドトップ